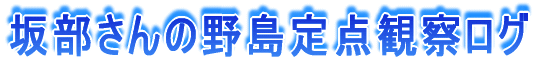
2008年6月21日
雨のち曇り 南風
視界 50cm 水温20℃
中潮 12:30 干潮


この2枚はオイルフェンスのところです。かなり赤潮でした。(写真提供:ボーデンさん)
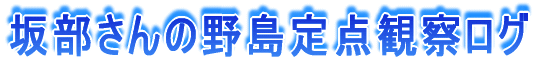
2008年6月21日
雨のち曇り 南風
視界 50cm 水温20℃
中潮 12:30 干潮


この2枚はオイルフェンスのところです。かなり赤潮でした。(写真提供:ボーデンさん)
引き網の生き物たち(確認できたもの)
メバル(成魚・稚魚)・海タナゴ(稚魚)・ヒガンフグ(稚魚)・ゴンズイ(大)ニクハゼ(大量)
アナハゼ・クジメ・セイゴ・カワハギ(稚魚)・ヨウジウオ・セイゴ(スズキの子供、成長にしたがって関東で はセイゴ・フッコ・スズキと呼び名が変わる)
ワレカラ
ウミナメクジ・ツノモエビ・ヒメイカ
ムシロガイ系の巻貝
イシガニ





その他
クロシタナシウミウシ(多分)・スミイカの甲・サメの卵の殻
干潟は、透明な風船(タマシキゴカイの卵)と砂モンブラン(その排泄物)で足の踏み場もないくらい。ゴカイは海のミミズだから、ゴカイの多いのはよい事だよね・・・と干潟遊びのメンバーの意見が一致。

マテガイが砂の上に顔を出しているのを実際にみるのは初めて。深めの水温の低い場所に移動させると元気回復。引き網に、巻貝が入ってきたのも、去年はなかったような気がする。赤潮の影響?
去年は、沢山いたメリベウミウシとヨウジウオの数が少ないのは、確かに気になる。
小指の爪ほどのアサリの稚貝はたくさん。砂の上においておくと、見る見るうちに砂に潜っていく。ある程度成長した貝よりも、反応速度が速いので、面白い。じっくり見ると模様も、幾つかのパターンに分けられる。
河内さんによれば、アサリの血統によってパターンが違うのだ、そうでその辺の勉強も楽しい宿題です。
大雨予報のため、駐車場からウエットスーツ着用、着替えも車に置いたままで出撃。しかし雨があがり、気温も上昇、上半身だけ脱いでオールクリーンに参加したけれど、終了時には熱中症一歩手前。ネオプレーンの保温力を甘く見ては、いけない。洗濯物が増えようとも、夏季の陸上作業は、ウエットスーツを脱いで行うべし!!
駐車場にて。
昨夜から停まっていたと隣のワンボックスの後ろには、鋤簾を含めた大掛かりなアサリ採りの道具の山。
帰宅前に、ウエットスーツと一緒に柵にぶら下がって川風に体温を下げてもらっていると、胴長着用でワンボックスの主が登場。
干潟のコメツキカニのパフオーマンスの可愛らしさに会話の花が咲くうち、ふとウエットスーツに目が留って
「潜っていたのですか?」
「アマモ場の調査で海にはいってました」
「アマモねえ、全国で賛否両論の・・・。自然のためにはいいことなんだろうけれど・・・ねえ」
外浦のアマモ根こそぎ駆除作戦のことをおっしゃっていらっしゃるのかしらん?
すべて物事には、色々な側面があるもので、一つの面だけ捉えてしまって追求すると、養老先生の「バカの壁」になる。アマモ場再生の意義と、地元の利害関係と、お互いの長所を認め合ってうまく折り合って行ければいいのに。
・・・・日本人の大好きな大岡越前の名裁きに、 三方一両損 なんてのがあるじゃございませんか。
以下 河内さんのコメント
巻貝ですが、巻貝は赤潮の影響で短期間に移動できる生物ではないので、
もう少し長期的に増えていると思います。
今回の巻き貝は貝殻の横幅5mm程度でしたが、
昨年は1〜2mmのものが見られていたと思いますので、
昨年よりも大型の巻き貝が引き網にかかったのでしょう。
大きな巻き貝=アマモが太くしっかりしたともいえますかね?
いかがでしょう。
それから、再び同様のアサリ取りの人と会う機会があったら、
「アマモがなかったら、あなたが採ったそのアサリも
数日前の赤潮で大量死していたかもしれませんよ。
実際に、マテガイの死がいが沢山あったでしょう。」
と言ってあげてください。
工藤さんからも、赤潮発生時、アマモ場の外側・内側で違いが見られ、
アマモ場と干潟の自浄作用の効果が見られたとの話がありました。
その水域の利用方法によって、良くも悪くもなりますが、
海水浴場ではないこの野島では、
色々な人がアマモの恩恵に助けられているはずです。
日本人はどこか成功すると、日本全国一律、同じことをやりたがりますが、
全国一律で同じことがベストではなく、
砂場にはアマモ、岩場には褐藻、観光地では・・・というように、
その地域にあった方法があるのですから。
PS.アサリの血統パターンは残念ながら私の話じゃないですよ。