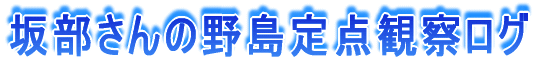
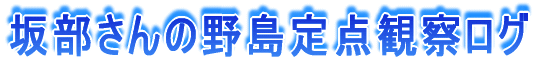
2008年9月28日
大潮 10:16干潮
北東の風・曇り 気温 18度 水温22−3度
☆引き網の生き物☆
ゴンズイ・ウミタナゴ・カタクチイワシの群れ・トウゴロイワシの群れ・カワハギ・アイゴ・アナハゼ・メバル・ギンポ・白魚風の魚・クロサギ・アシナガモエビ・ツノモエビ・アミメハギ・ヨウジウオ・ヒメイカ・ホンベラ(背びれにスポットがあったので多分)




ゴンズイ カワハギ アイゴ アサヒアナハゼ


ツノモエビ ホンベラ
☆特筆すべきはイサキの稚魚
私自身はイサキの稚魚を引き網で確認するのは初めて。
イサキの稚魚は、内湾の水深5−10m位のアマモ藻場あるいは海藻の多い岩礁と砂底の境界域を群泳している。
From:日本の海水魚 山と渓谷社
という記述があるので、この子がここに居た、ということが、アマモ場効果の現れの一つだと嬉しいな、と思う。
ほかにクロサギ(存在さえ知らなかった魚)、白魚風の魚、種類が分からない稚魚が数匹いたので、工藤さんの調査結果がとても楽しみ。


シマイサキ クロザギ
そのほかアケボノチョウチョウウオ・トノサマダイ・イシダイ・クロダイ・スズキ・ヒラメ・カレイ・カニを食べているタコが目視されている。
浅瀬にいたコトヒキの幼魚たちの姿がない。
あれほど沢山居たギマが姿を消してしまった。ウミナメクジも網に入らない。みんなどこに行くのだろう。
次の夏には、また戻ってきてくれますように!!
☆運悪く?成長したゴンズイ球を網にかけてしまったので、四個の採集壜はギッチギチに満杯。
引き網にかかった生き物たちは、すべてホルマリンで固定され、アマモ場にどれほどの生き物が増えていく過程を証明する資料になってもらうのだ。合掌。
生まれ変わったら、もっと豊かになったアマモ場に戻ってきてほしい。そして、その時には引き網が必要でなくなっていて、みんな自然の寿命を全うできますように。
今日の沢山の命たちが、干潟の保全、海の環境改善の機運を更に後押ししてくれるでしょう by 福島さん
☆海のステルス・ヒメイカ☆
ヒメイカ
胴長1.5センチ 房総半島―九州。鰭は小さい。外套膜の背面後端近くに粘液細胞があり、それで体をアマモや海藻にくっつける性質がある。
軟・頭足類 ヒメイカ科 From:海辺の生きもの 山と渓谷社
小さな小さなヒメイカは、アマモの葉裏にくっついて隠れているので、スキンはおろかスキューバでも見つけるのは難しい。私達がヒメイカを観察することができるのは、引き網に引っかかってくれた時しかない。今日、観察ケースの中で、ヒメイカが、墨を吐くのを見ることができた。
吐かれた墨は、ヒメイカと同じ大きさの球形を保ったまま、五分ほど水の中に漂ってからゆっくりほぐれていった。
潜水艦や戦闘機が発射するデコイである!(実際は人間がマネをしているのだけど)
私
の釣りの師匠によれば、スミイカは墨を煙幕にして逃げ、アオリイカはヒメイカと同じくデコイ戦法で、敵から逃げる。墨の粘性は、アオリイカの方がずっと高
いとのこと。イカの墨がチャフやデコイの役目をするのは知っていたけれど、実際に見るのは初めてだし、小さな小さなヒメイカでさえも、そんな能力を備えて
いるなんて。ヒメイカ凄い!!!


ヒメイカ イカスミ
こんな風に毎回なにかしら新しい感激があって、ますます野島の海にハマっていくのです。
透明なアクリルの観察ケースは、写真を撮るのにも、立体的に生き物を観察するのにも、非常に役に立つ海辺の道具です。
Special thanks to 弘明寺の水槽屋さん!
(写真提供:伊東)
☆ヒート・ロス注意報☆ from:CNAC安全講習
これからの野島は、北風が強く吹きます。
水は空気の25倍の熱伝導率だし、ドライでもウエットでも、濡れた体で風に吹かれれば気化熱が奪われて、更に体温が下がります。
SCUBAチームにも、引き網チームにも、辛い季節がすぐそこまで来ています。
海辺に来る時は、風を通さないウインドブレーカーのようなものを必ず持ってきてください。
震えが来たり、手足がしびれてきたら、さっさと海から上がって、乾いたものに着替えて、暖かい飲み物や甘いモノで、熱量を補いましょう。
海に入る前に、消費するカロリーを見越して、甘いモノをとっておくのもお勧めです。
日常的に海で仕事をしている人に比較して、ホリデー・ダイバーは、寒さ・暑さに対する耐性がずっと低いのです。
海でのやせ我慢は禁物。自分の身体能力を理解して、しっかり体調管理しましょう!!
☆早川丸の船長さん☆
アサリとアナゴ漁師の早川さん。県の委託を受けてアマモ場再生活動をバックアップしてくれています。
豊富な経験と知識と発想力の持ち主の、海の大達人。早川さんが見守っていてくれるおかげで、私達は安心して海に入る事ができるのです。
 早川さん (写真提供:坂本事務局長)
早川さん (写真提供:坂本事務局長)
ある朝。
海から、早川丸に這い上がると、「ほらあ、見てごらん!」
待つ手も遅しと、生簀の蓋を開けてくれる早川さん。
ゆったり泳いでいたのは、蛍光紫が鮮やかな、それは見事なソウシハギ。
「きれいだろ、この縞の色がね、桔梗の花みたいだろ? だから、わたしはソウシハギが好きなのかもしれないな」
海の大達人は、詩人です。